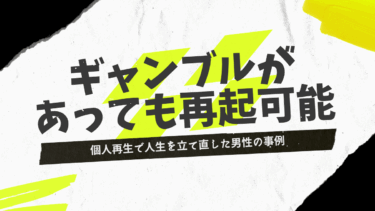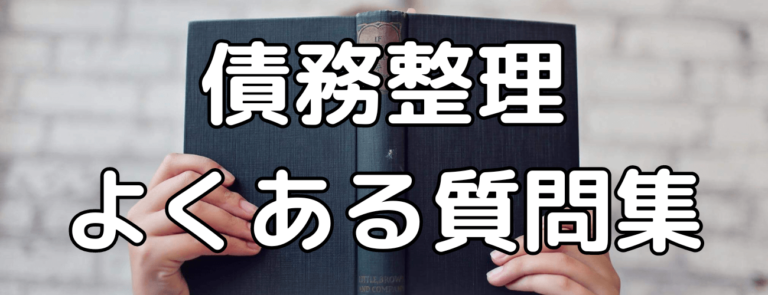個人再生とは…
借金総額を大幅にカットし、原則3年(最長5年)で弁済していくことができる方法です。
住宅資金特別条項が使えれば、あなたのマイホーム(住宅ローン)を維持して、その他の借金だけを大幅に減額できます。また、実際に財産を処分することはありません。
個人再生手続きを選択するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
・住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円未満であること
・安定した収入があること
まず、この2つの条件をクリアしていることが前提です。
そして、重要になるのが…
清算価値が最低弁済額になること
あなたの財産をもしもお金に換えたらいくらになるのか?ということです。
この清算価値の金額次第で、個人再生手続きを行う意味がなくなってしまうことがあります。
個人再生は、多重債務に悩む方にとって、借金を大幅に減額できる有効な手段です。
しかし、この手続きを進める中で、知らないうちに落とし穴にはまってしまい、個人再生が「できない」状況に陥る可能性もあります。
この記事では、個人再生の失敗を避けるために押さえておくべき4つの重要なポイントを解説し、どのように進めるべきかを具体的に紹介します。
また、当事務所のサポート体制を活かして、安心して手続きを進める方法もご提案します。
まずは、個人再生の基本的なリスクと、どのようなケースで「できない」事態が起こるのかを確認していきましょう。
個人再生が「できない」理由とは?
個人再生は、借金返済の負担を大幅に軽減できる一方で、手続きを進めるにあたってはさまざまな条件を満たす必要があります。
これらの条件をクリアできない場合、個人再生の申し立てが受理されず、結果的に「失敗」につながることがあります。
ここでは、個人再生ができない理由を具体的に確認し、そのリスクを最小限に抑えるために知っておくべき要点を解説します。
個人再生を失敗しないための4つのポイント
個人再生の成功には、いくつかの重要な条件が関わります。この章では、失敗を避けるための4つのポイントについて詳しく説明します。これらを理解しておくことで、個人再生の手続きをスムーズに進めることができます。
1.借金総額には限度がある
個人再生手続きは、下記の借金総額に基づいて最低弁済額が決まっています。
最低弁済額とは、債権者に最低限返さなくてはいけない返済額のことです。
| 最低弁済基準額 | |
| 借金の総額 | 最低弁済額 |
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円~500万円未満 | 100万円 |
| 500万円~1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
| 1,500万円~3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000万円~5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
この表の中で、個人再生を選択できない明確な理由が2つあります。
借金総額が100万円未満の場合
借金総額が100万円未満の場合は、全額弁済となるので、個人再生を選択する意味がありません。
1円も減額されないということです。
100万円未満の借金でお困りの場合は、任意整理を選択されるのが賢明です。
また、状況によっては、自己破産の方が良いでしょう。
借金総額が5,000万円以上の場合
個人再生には、減額を受けられる借金総額に上限があります。その上限は、5000万円以下の借金が対象となり、それを超える場合は個人再生の適用外です。
万が一、借金総額が上限を超えている場合は、他の債務整理方法を検討する必要があります。
借金総額が気になる場合は、当事務所にご相談いただければ、最適な方法をアドバイスいたします。
2.個人再生を選択するには安定した収入が必要
個人再生を進めるためには、継続的かつ安定した収入が必要です。
これは、借金を減額した後も一定の返済を行うことが前提となるためです。収入が不安定な場合、手続きが進まない可能性が高いので、まずは収入面の確認を行いましょう。
個人再生手続きは、裁判所を通して、毎月減額された借金を支払っていくことを債権者と約束することになります。
この約束をするためには…
「毎月支払っていくことができます」
という証明が必要になります。
その証明方法は、履行テストと呼ばれる毎月の積立金をして、「毎月支払っていくことができます」という返済のデモンストレーションです。
さらに、履行テストは問題なくできていますという証として、家計収支表をつけます。
これらを達成しようと思うと、毎月滞りなく支払える収入が必要です。
その収入源は、何となくでは裁判所は認めてくれません。
だから、安定した収入が必要になるわけです。
・正社員
・派遣社員(雇用期間の見通しが立てばOK)
・パート、アルバイト(勤続、勤務実績があればOK)
・個人事業主、歩合給(増減しても弁済見込みが立てばOK)
・年金受給者
生活保護受給者、主婦(主夫)は、個人的な収入とは判断されないため、安定した収入の要件には該当しません。
3. 住宅ローンのアンダーローンが適用されること
個人再生は、特殊な性質を持っています。
住宅資金特別条項の要件を満たしていれば、住宅ローンを支払い続けて、その他の借金を大幅に減額することが可能です。
ここで、2つのことをピックアップします。
アンダーローンの場合
住宅資金特別条項を使うためには、オーバーローンである必要があります。
つまり、住宅の価値がローンの残債を上回ったら使えません。
これをアンダーローンと言います。
アンダーローンだった場合は、その住宅の価値を清算価値として計上しなくてはいけないため、最低弁済額が大きく上がることになります。
大幅な減額を目指す個人再生としては、アンダーローンは不向きです。
住宅ローンがない場合
住宅資金特別条項は、住宅ローンを持っている人が対象のため対象外です。
住宅ローンを完済している場合は、住宅の査定をします。
その査定額が、清算価値として弁済額に影響します。
本来ならば、最低弁済額は100万円となりますが、住宅の価値が500万円だった場合は、最低弁済額は500万円のままとなります。
個人再生を利用するのであれば、借金額よりも住宅の価値が下回らないと意味がありません。
住宅ローン特則を利用して家を守りたい場合、住宅ローンがアンダーローン(物件価値よりもローン残高が大きい状態)である必要があります。
これに該当しない場合、住宅ローン特則が適用されず、家を手放さざるを得ないリスクがあります。
当事務所では、この点についてもしっかりと確認し、住宅ローン特則の適用が可能かどうかを詳しくご説明します。
4. 財産を所持しすぎていると減額率に影響
個人再生手続きは、実際に財産を処分することはありません。
※所有権留保の問題で、持っている車などが引き揚げられることはあります。
再生計画案を立てる際に、プラスの財産を計算することになります。
この時、プラスの財産として計算されたものは、清算価値として計上することになります。
つまり、プラスの財産を持っていれば持っているほど、清算価値は高くなり減額されない状況になります。
例えば、学資保険や生命保険の解約返戻金などが該当します。
借金総額が300万円位対して、学資保険が200万円、生命保険の解約返戻金が50万円だった場合…
清算価値は、250万円となります。
この清算価値の250万円を3年または5年で分割して弁済することになります。
個人再生では、財産を持ちすぎていると、その価値に応じて返済額が上がる可能性があります。
具体的には、所有する資産が高額である場合、借金の減額率が下がり、返済負担が大きくなることがあります。
財産の処分や適切な管理を含めたアドバイスを行い、できるだけ有利な条件で個人再生を進められるよう、当事務所がサポートいたします。
個人再生を選択できないと判断された場合にできること
上記に書いた条件のどれかに当てはまっていた場合は、個人再生手続きを選択することができなかったり、無意味になってしまうことがあります。
この場合に弁護士が提案できることは3つです。
★民事再生を検討する
★自己破産を検討する
個人再生手続きが選択できなかったとなったとしても、借金でお困りの状況であることは変わらないですよね。
この3つの中から、あなたの状況に合った手続きを弁護士と話し合うことが必要です。
Aという選択をした時、どのようなことが起こるのか…
Bという選択をしたら、こうなります。
こういったことを提案するのが弁護士の仕事の1つです。
個人再生手続きができないからといって諦めないでください。
当事務所のサポート体制と強み
個人再生の手続きを進める中で、どのような落とし穴が潜んでいるかを理解していても、一人で対処するのは難しいものです。
当事務所では、経験豊富な弁護士と専属スタッフが、個人再生のプロセス全体をサポートします。各ステップにおけるリスクをしっかりと把握し、失敗のリスクを最小限に抑えるための具体的なアドバイスを提供します。
さらに、当事務所では、相談後のサポートも充実しており、債務整理が完了するまでの安心できるサポート体制を整えています。個人再生に関する不安や疑問点をすべて解消し、確実に手続きを進めるために、まずはお気軽にご相談ください。
結論|個人再生を検討するなら、当事務所にご相談を
個人再生を成功させるためには、各ステップで注意すべきポイントを押さえることが重要です。
当事務所では、個別の事情に合わせたアプローチを提供し、安心して手続きを進められる体制を整えています。まずは、無料面談相談から始めてみましょう。専門家があなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案いたします。
<今日のおさらい>
- 個人再生できる借金の金額が決まっている
- 個人再生を選択するには安定した収入が必要
- 住宅ローンを守るには住宅資金特別条項の要件を満たす必要がある
- 財産が多すぎると減額ができない
個人再生ができないと判断される4つのポイントについては以上です。
個人再生を進める中での「落とし穴」とは、しっかりと知識を持ち、適切なサポートを受けることで避けることができます。
個人再生に不安がある方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。専門的なアドバイスと安心できるサポート体制を通じて、あなたの経済的な再出発を全力でサポートいたします。
当事務所、アーク法律事務所へのご相談には来所が必要です。
場所は、名古屋市中区丸の内3丁目17番地13号 いちご丸の内ビル6階にあります。
地下鉄「久屋大通駅」1番出口より北へ徒歩1分です。
面談時間は、平日10時より行っています。
平日夜間・土日にも対応しています。
ご相談料は不要です。
何度ご相談いただいても、セカンドオピニオンのご相談も無料です。
借金のご相談は、債務整理に注力している弁護士をお尋ねください。
<成功事例>
個人再生の成功事例|借金大幅ダウンで財産も守れる優れた手続き
<個人再生をお考えの方へ>
<債務整理をお考えの方へ>
| 債務整理とは何のこと?わかりやすく図解を使って説明します! |
| 【債務整理】弁護士と司法書士の違いや費用について |
| 債務整理|弁護士の選び方「3つの失敗しない重要ポイント」 |
| 弁護士費用の比較|債務整理の費用の相場はどのくらい? |
| 債務整理の相談時に必要なものは?弁護士が1番教えて欲しいこととは… |
| 債務整理のおすすめの手続きは?自分に合う方法の選び方 |
| 自己破産・個人再生|弁護士に相談前の事前準備・知識について |




FXなどの投資で借金ができた時の解決方法-375x222.webp)