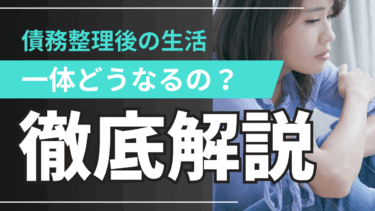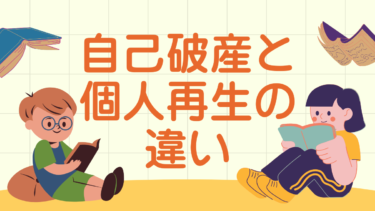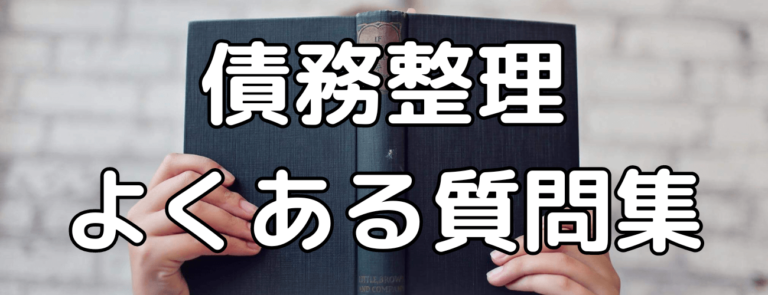1回目にやった債務整理の完済がまだ終わってないのにまた支払いに困ってしまった。
以前に自己破産してるけど、また債務整理をすることはできるんだろうか?
こんな自分の話を聞いてくれる弁護士や司法書士はいるのだろうか?
借金の問題は、一度解決したとしても、再度困る事態に直面することは珍しいことではありません。
収入状況が変わったり、任意整理で頑張れると思ったけど無理だったという結果を迎えたり、様々なケースがあります。
ただ、心理的な問題は、1回目よりも2回目の方が複雑化することもあります。
弁護士や司法書士選びに関しても、一度手続きをしてもらった事務所に相談しにくいと感じる人も多いものです。
場合によっては、債務整理の経験が浅い弁護士や司法書士のアドバイスで、先に行った任意整理が〝失敗したかも〟と感じることもあるかもしれません。
これは、任意整理をしたものの生活再建に繋がらなかったという結果が起きたことによります。
よって、債務整理の相談相手は、債務整理の経験値の高い弁護士が好ましいと思います。
まず、あなたにお伝えしたいことは
ケースによっては、どの債務整理を選べばいいのか難しいこともありますが、あなたに寄り添って考えることが僕のモットーです。
実際「以前に債務整理をお願いしたのですが…」と再相談にいらっしゃる方も多数いますので、どうぞご安心ください。
中には、正義感にあふれて、2回目の自己破産だと快く思わない弁護士もいるかもしれません。
もし、そんな弁護士や司法書士に当たった時には、諦めずに別の弁護士に相談してくださいね。
何度目の債務整理でも真摯に対応する弁護士もたくさんいます。
あなたの明るい未来を得ることが1番大事なことです。
では、2回目の債務整理の条件や注意点、知っておくべきことなどをまとめていきたいと思います。
2回目の債務整理をする場合、同じ弁護士と違う弁護士どっちが好ましいのか?
冒頭でも書きました。
あなたが気にならなければ、同じ弁護士に相談くださるとメリットが大きいと思います。
②次の手立てを考えるうえで、何を改善すべきか見えやすい
あなたが以前にやった債務整理の資料が残っていた場合は、今後の債務整理の検討がしやすかったり、どのような対策ができるかを練りやすくなりますので、メリットが大きいです。
※以前の債務整理が5年以上前だと、資料が事務所に残されていない場合もあります。
では、具体的な手続きについて説明します。
2回目の債務整理の注意事項
共通している注意事項を先に書きます。
2回目の債務整理を行うと時、3つの注意点があります。
- ブラックリスト(信用情報機関)に事故情報として登録される期間が長引くケースがある
- 前回の費用は返ってこない
- 前回の手続きによって2回目の債務整理の可否が異なる
■信用情報について
通常、債務整理後、完済から5年で事故情報が消えるとされています。
しかし、完済に至っていない状況で、2回目の債務整理を行うと、事故情報が抹消されないまま掲載期間が延びることが予測されます。
単純計算は、前回の債務整理から今日までの年数+5年とお考え下さい。
■前回の債務整理費用
債務整理ご依頼中の方針変更であれば、費用の差額で済むと思いますが、一度、債務整理を行ってしまった後の再相談の場合は、前回の債務整理費用が返ってきたり、差額で依頼ができるということは残念ながらありません。
これ以上の費用を発生させないためにも、債務整理の経験豊富な弁護士にご相談ください。
■2回目の債務整理の可否
次に2回目の債務整理の注意点について、種類別に細かく解説しますのでお読みください。
任意整理2回目の条件と注意点
任意整理→任意整理
任意整理には、回数制限はありません。
ですが、任意整理の2回目以降の注意点は、一度目の任意整理に応じてくれたとしても、債権者によっては二度目の和解交渉に応じてもらえない場合があります。
さらに、滞納している場合は、遅延損害金が加算されたり、頭金や利息を付けないと債権者の納得が得られないことも考えられます。
頭金・利息・期間の短縮は、1回目の任意整理でも和解条件に含まれるケースが増えていますので、2回目も同じように上手くいく保証はありません。
つまり、1回目の任意整理の弁済額より高くなる可能性が十分にあり、場合によっては2回目の任意整理に応じてくれない債権者がいるということを考慮してください。
任意整理→個人再生
任意整理から個人再生を選択するには、安定した収入があって、返済の見込みがあるのであれば十分検討できます。
また、住宅ローンを抱えていてもオーバーローンの場合には、住宅を処分せずに済む可能性があります。
実際に財産の処分をすることもないので、安定した収入のある人にはメリットの高い手続きです。
ただし、個人再生を検討する場合
返済不能になった時、特定の債権者にだけ返済することや勝手に財産を処分することは禁止されているのでご注意ください。
(これを偏波弁済と言います)
偏頗弁済とは、返済不能になった時、「この借金だけは返さなくてはいけない」と思うと、他の借金を後回しにしてしまうことがあります。
これは、債権者を平等に扱っていない行為としてみなされてしまいます。
また、裁判所に財産を取られたくないと勝手に処分してしまう行為は禁止されています。
個人再生では、実際に財産を処分することはありません。
財産相当分を清算価値といって、弁済額に組み込みます。
よって、財産を多く持っている場合は、個人再生をする意味がなくなってしまうことがあります。
任意整理→自己破産
扱いは、1回目の自己破産ですので、任意整理後に自己破産をすることは可能です。
ただし、税金・健康保険料・損害賠償金・養育費などは、免責(帳消し)の対象外となります。
また、一部の職業(士業・金融関係の職)の人には、資格の制限が設けられており、自己破産を選択できない場合があります。
自己破産には、借金の原因によって手続きの流れが変わります。
特に借金の原因に問題がない場合には、同時廃止事件として扱い6~7ヶ月ほどで手続きは終わります。
ギャンブル・投資・浪費が原因の場合には、管財事件という扱いになり、裁判所に支払う予納金の額が高くなり、手続き期間(1年弱を目安)も長くなります。
これは、免責不許可事由に該当することで起きますが、更生して生活再建をしていくという意思が認められれば、免責を得ることは可能です。
思うほど処分されてしまうものはないはずです。
どの手続きを依頼しても、買った商品などが引きあげあれるかは、所有権留保という契約がカギを握っています。
これは、所有権が誰にあるのかというものです。
例えば、車のローンがある場合、車検証に使用者と所有者が別の記載をされていると思います。
この所有者が「その商品は引きあげます」と言えば、返還しなくてはいけないものであるということを指します。
引きあげられたものは売却をし、返済されなかった分のお金に換えるため、所有者の意向に従わなくてはなりません。
個人再生2回目の条件と注意点
小規模個人再生の場合
1回目の個人再生が小規模個人再生であった場合、制限を受けることはありません。
再度、小規模個人再生をすることも可能です。
給与所得者等再生、自己破産を選択することも可能です。
ただし、2度目の小規模個人再生を行う場合は、債権者から不同意を得やすい状況にあることを頭に入れておいてください。
1度目では不同意しなかった債権者も2度目になると不同意をすることもあります。
給与所得者等再生の場合
1回目が給与所得者等再生をした場合、2回目に小規模個人再生または自己破産を選択することは可能です。
ですが、
2回目も給与所得者等再生を選択することは7年間できません。
自己破産2回目の条件と注意点
自己破産をした人が2回目の債務整理をすることは可能です。
任意整理、個人再生を選択することは制度上問題ありません。
借金にお困りならば、ご相談ください。
しかし、2回目の自己破産をする場合は、7年以上期間が空いていることが好ましいです。
費用については、管財事件となる可能性が非常に高くなりますので、弁護士費用に加えて、予納金(20~40万円)がプラスされると考えておいてください。
「免責許可」がもらえるかは別の問題となるので、弁護士と十分相談の上でどのようにしていくのか対策が必要となります。
裁判所が「免責許可」を出すかどうかは、十分考慮できる事情があったかにかかっています。
不幸な理由で、前回の自己破産から7年経たずに、2回目の破産の申立をし、免責許可を得たこともあります。
裁判所に認めてもらえる理由があれば、心配しなくても大丈夫です。
まとめ|債務整理の回数よりも借金の理由の方が重要!
再び借金に困ってしまった時、弁護士にきちんと今の状況を伝えるということが、今後のあなたの人生の明暗を分けることになります。
・給与所得者等再生
・自己破産
どちらかを1回目の債務整理で行っている場合は、原則7年以内の再度同じ手続きの申立は不可となっています。
ですが、上記で書いたようにあなたの状況によっては、2回目の債務整理であっても裁判所は認めてくれます。
あなたの借金が増幅した背景に一体どんな問題が隠れているのかが、一番の大事なポイントになります。
浪費・ギャンブルがやめられなくて増えてしまったのなら、そこから見直し改めていかなくてはなりません。
そして、そういうことも含めて、あなたを見放すことなく、今後はどのようにしていくべきなのかを一緒に考えていくのが、弁護士の仕事の1つです。
詳しい状況は、面談にてお聞かせください。
ご相談だけでも大丈夫です。
何度でも無料で面談相談を行っています。
<成功事例>
個人再生の成功事例|借金大幅ダウンで財産も守れる優れた手続き
<債務整理をお考えの方へ>
| 債務整理とは何のこと?わかりやすく図解を使って説明します! |
| 【債務整理】弁護士と司法書士の違いや費用について |
| 債務整理|弁護士の選び方「3つの失敗しない重要ポイント」 |
| 弁護士費用の比較|債務整理の費用の相場はどのくらい? |
| 債務整理の相談時に必要なものは?弁護士が1番教えて欲しいこととは… |
| 債務整理のおすすめの手続きは?自分に合う方法の選び方 |
| 自己破産・個人再生|弁護士に相談前の事前準備・知識について |